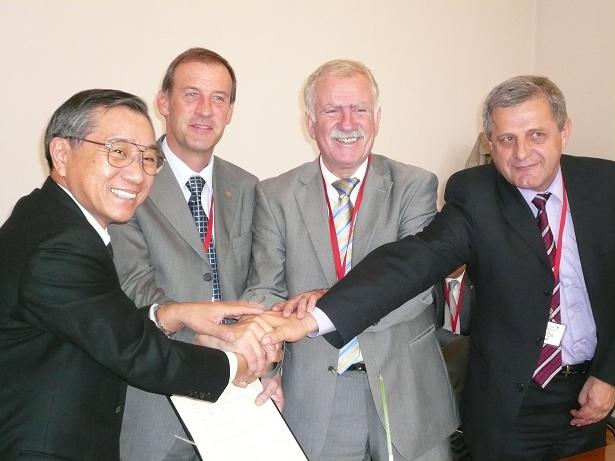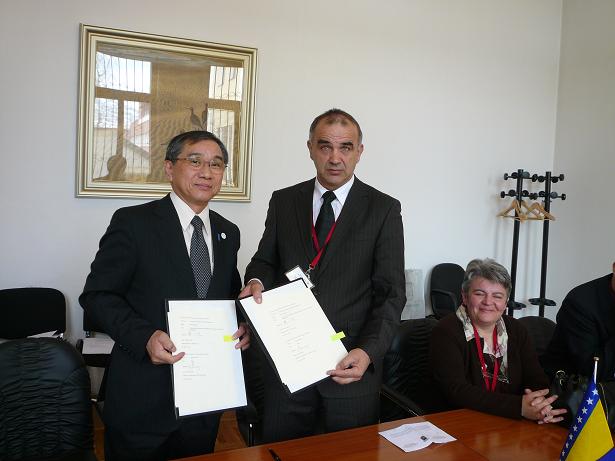2009年12月14日
草の根無償資金協力による「ゼニツァ市アレクサ・シャンティチ小学校暖房修復計画」 引渡式実施
-
12月14日、罍二夫大使は、サラエボの北北西約80キロに位置するゼニツァ市にて「ゼニツァ市アレクサ・シャンティチ小学校暖房修復計画」(50,988ユーロ(8,362,032円))の引渡式に出席しました。 式典には、ガリヤシェヴィッチ・ゼニツァ-ドボイ県首相、メルジャン・ゼニツァ-ドボイ県教育省大臣、セルマノヴィッチ・ゼニツァ-ドボイ県教育委員長、スマイロヴィッチ・ゼニツァ市長も参列しました。
-
この案件において日本政府は、アレクサ・シャンティチ小学校に対し、セントラルヒーティングを新しいボイラーと共に整備し、30年以上使用している生徒用の机・椅子も整備しました。 この計画により、全校生徒約1200名と教職員75名の教育環境と保健衛生環境が改善されます。
-
日本政府は2009年、アレクサ・シャンティチ小学校を含むボスニア・ヘルツェゴビナの3つの小学校の教育環境改善計画を実施しています。 1996年から現在に至るまで日本政府は、同国の初等教育整備のために約2千万ユーロを支援しています。
-
引渡式に先立ち、罍大使はゼニツァ-ドボイ県庁舎を訪問し、ガリヤシェヴィッチ・ゼニツァ-ドボイ県首相、メルジャン・ゼニツァ-ドボイ県教育省大臣と会談しました。
2009年12月14日
草の根無償資金協力による「ムラ・ムスタファ・バシェスキヤ小学校修復計画」 引渡式実施
-
12月14日、罍二夫大使は、サラエボの北北西約55キロに位置するカカニ市にて「ムラ・ムスタファ・バシェスキヤ小学校修復計画」(61,344ユーロ(9,017,568円))の引渡式に出席しました。 式典には、メルジャン・ゼニツァ-ドボイ県教育省大臣、セルマノヴィッチ・ゼニツァ-ドボイ県教育委員長、ヤシャルスパヒッチ・カカニ市長も参列しました。
-
この案件において日本政府は、ムラ・ムスタファ・バシェスキヤ小学校に対し、校舎屋根と体育館外壁の修復及び学校玄関の整備を支援しました。 この計画により、全校生徒約1200名と教職員75名の教育環境と保健衛生環境が改善されます。
-
日本政府は2009年、ムラ・ムスタファ・バシェスキヤ小学校を含むボスニア・ヘルツェゴビナの3つの小学校の教育環境改善計画を実施しています。 1996年から現在に至るまで日本政府は、同国の初等教育整備のために約2千万ユーロを支援しています。
-
引渡式に先立ち、罍大使はカカニ市庁舎を訪問し、ヤサルスパヒッチ・カカニ市長と会談しました。
2009年12月2日
草の根無償資金協力による「ドニ・ヴァクフ第一小学校教育環境改善計画」 引渡式実施
-
12月2日、罍二夫大使は、サラエボの北西約130キロに位置するドニ・ヴァクフ市にて「ドニ・ヴァクフ第一小学校教育環境改善計画」(60,966ユーロ(9,998,424円))の引渡式式典に出席しました。
-
この案件において日本政府は、ドニ・ヴァクフ第一小学校クリチャ・クラ分校に対し、今までの薪ストーブからセントラルヒーティングを導入した新しい暖房設備を設置し、また本校のドニ・ヴァクフ第一小学校には机と椅子を整備しました。 この計画により、全校生徒1216名と教職員73名の教育環境と保健衛生環境が改善されます。
-
日本政府は2009年、ドニ・ヴァクフ第一小学校を含むボスニア・ヘルツェゴビナの3つの小学校の教育環境改善計画を実施しています。 1996年から現在に至るまで日本政府は、同国の初等教育整備のために約2千万ユーロを支援しています。
-
引渡式に先立ち、罍大使はドニ・ヴァクフ市庁舎を訪問し、スシッチ ドニ・ヴァクフ市長及びタリッチ同市議会議長と会談しました。
2009年11月24日
グラチャニツア市における地雷除去作業費用 20万ユーロを支援
-
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館の罍二夫大使は、ITF(International Trust Fund for Demmining and Mine Victims Assistance:地雷除去と地雷による被害者救済のための国際信託基金)との間で、「グラチャニツァ市における地雷除去作業支援計画」の贈与契約を締結しました。 これは日本政府の「草の根・人間の安全保障無償資金協力」を通じ、トゥズラ県グラチャニツァ市の地雷汚染推定地域200,000平方メートルにおける地雷除去作業を行うため、200,000ユーロ(約28,600,000円)を支援するものです。
-
ITFはスロベニアに本部を置く非営利団体で、1998年に設立されて以来、南東欧地域における地雷除去活動を中心に、地雷回避教育と地雷による被害者のための支援を実施しています。
-
ボスニア国内にはまだ22万個の地雷・不発弾が埋まっていると推測されているため、インフラ整備が進まず難民・国内避難民の帰還が遅れる原因となっています。 ボスニア北東部のグラチャニツァ市では、市内を流れるスプレチャ川流域に地雷が多く埋設されているおり、肥沃な農耕地が利用できないことで地域の経済発展の妨げとなっています。 本計画ではITFからも20万ユーロが拠出され、日本政府からの支援と合わせて40万ドルの合同事業となり、合計約38万平方メートルの地域の地雷が除去され安全が宣言される予定です。
-
日本政府は1996年にボスニア・ヘルツェゴビナへの支援を開始して以来、100万ユーロ以上を地雷除去作業と地雷回避教育のために支援しています。
2009年10月29日
草の根無償資金協力による「バノヴィチにおける地雷除去作業支援計画」 引渡式実施
-
10月29日、罍二夫大使はサラエボの北約130キロに位置するバノヴィチ市にて「バノヴィチにおける地雷除去作業支援計画」(152,319ユーロ(24,980,316円))の引渡式式典に出席しました。
-
この案件において日本政府は、バノヴィチ市郊外50,500平方メートルにおける地雷除去作業費用を支援しました。 この計画は、地雷汚染推定地域に埋設されている地雷を除去し、安全な農地へのアクセスを可能とし、地域住民の農業活動と地域の経済開発を促進することを目的としています。 更に、地域住民がより安全で平和な日常生活を取り戻し、先般の紛争で被害を受けたバノヴィチ市への帰還民定着を促進することも期待されています。
-
尚 作業期間中、7つの地雷・不発弾などが発見され安全に処理されました。
-
日本政府は1996年にボスニア・ヘルツェゴビナへの支援を開始して以来、100万ユーロ以上を地雷除去作業と地雷回避教育の支援のため、ボスニア・ヘルツェゴビナ地雷対策センター(BHMAC)に支援しています。
-
引渡式後、罍大使はバノヴィチ市庁舎を訪問し、ビルパリッチ・バノヴィチ市長と会談しました。 会談には、ムイッチ・トゥズラ県首相も同席し、本件への謝意を表明しました。
2009年10月29日
草の根無償資金協力による「ペトロヴォ市オズレン診療所医療機器整備計画」 引渡式実施
-
10月29日、罍二夫大使は、サラエボの北約200キロに位置するペトロヴォ市にて「ペトロボ市オズレン診療所医療機器整備計画」(54,116ユーロ(8,875,024円))の引渡式式典に出席しました。
-
この案件において、日本政府はペトロヴォ市オズレン診療所に対し、救急車両と初期治療に欠かせない検査機器-血液分析器、X線写真現像機、生化学検査器、遠心分離機、顕微鏡、心電図計などを供与しました。 本計画により新しい救急車両が、緊急搬送体制を向上させ、検査機器類が正確な検査結果を迅速に提供することにより、医療現場の環境向上と人口1万人のペトロヴォ市の地域医療環境の改善に貢献することが期待されます。 日本政府はボスニア・ヘルツェゴヴィナに対し1996年から現在まで、約5千万ユーロに及ぶ医療環境整備支援を行っています。
-
引渡式に先立ち、罍大使はペトロヴォ市庁舎を訪問し、ブラゴエヴィッチ・ペトロヴォ市長と会談しました。
2009年8月13日
大使がエコ・ツーリズム振興プロジェクト・サイトを訪問
-
8月13日、罍二夫大使は、日本政府が技術協力支援を行っているモスタル市内のブラガイ地区、ポドヴェレジュ地区及びネヴェシニエ市を訪問しました。この訪問において、大使はオメル・パイッチ・モスタル副市長、ブラニスラヴ・ニコヴィッチ・ネヴェシニエ市長、ならびにプロジェクト関係者と会談し、現在実施中である日本の技術協力「ボスニア・ヘルツェゴビナにおけるエコ・ツーリズムの持続的発展」プロジェクトの展望について協議を行いました。
-
エコ・ツーリズム分野におけるJICA専門家のリーダーを務める伊藤金雄氏もこの訪問に同行しました。日本政府及びJICAの経済協力の一環として本プロジェクトが2007年2月に開始されて以来、伊藤氏は他の専門家とともにエコ・ツーリズムを発展させようとしている地域住民の努力を支援しています。日本は本プロジェクトに人材育成の経費も含め、1,647,000ボスニア・マルク(約1億200万円)支援しています。
2009年8月12日
草の根無償資金協力による「ゼニツァ診療所救急車整備計画」 引渡式実施
-
8月12日、罍二夫大使は、サラエボの北北西約80キロに位置するゼニツァ市にて「ゼニツァ診療所救急車整備計画」(48,098ユーロ(7,888,072円))の引渡式式典に出席しました。
-
この案件において、日本政府はゼニツァ診療所に対し、除細動器、心肺蘇生セット、心電図計、吸引器、強力ライトなどを含む医療機材が搭載された高機能救急車を供与しました。 この救急車は山間部や道路事情が悪い場所、積雪の多い場所に素早く対応できるよう前輪駆動車となっており、人口13万人のゼニツァ市の地域医療環境の改善に貢献することが期待されます。 日本政府はボスニア・ヘルツェゴヴィナに対し1996年から現在まで、約5千万ユーロに及ぶ医療環境整備支援を行っています。
-
引渡式に先立ち、罍大使はゼニツァ市を管轄するゼニツァ-ドボイ県庁舎及びゼニツァ市庁舎を訪問し、ミラレム・ガリヤシェヴィッチ県首相とフセイン・スマイロヴィッチ-ゼニツァ市長と会談しました。 ガリヤシェヴィッチ首相とスマイロヴィッチ市長も引渡式式典に出席しました。
2009年8月12日
草の根無償資金協力による「ペチュイ地域水道整備支援計画」引渡式実施
-
2009年8月12日、罍二夫大使は、ボスニア中央部に位置するノヴィ・トラヴニク市ペチュイ地区において、「ペチュイ地域水道整備支援計画」(53,230ユーロ(8,729,720円))の引渡式式典に出席しました。
-
この案件において、日本政府は山の上にある貯水場から5つの村々へ合計15キロを結ぶ水道管設置を支援し、約1,000人の帰還民が安全な水を一年を通じて確保できるようになりました。 日本政府はボスニア・ヘルツェゴヴィナに対し1996年から現在まで、約95万ユーロに及ぶ水道関連事業支援を行っています。
-
引渡式に先立ち、罍大使はノヴィ・トラヴニク市庁舎を訪問し、レフィック・レンド-ノヴィ・トラヴニク市長と会談を行いました。 同市長と市議会議長も本引渡式式典に出席しました。
2009年6月24日
南ドボイ市が日本大使館を表彰
-
6月24日、ボスニア地方北部の南ドボイ市のジャヴィド・アリチッチ市長が当館に罍大使を来訪しました。アリチッチ市長は大使に対し、同市の最高位の市民賞と「南ドボイ市の盾」を手渡しました。これらの賞は、同市内のマトゥジチ地区にある「3月21日小学校」が日本政府の支援で建設されたことに感謝の意を表するために表彰されたものです。
-
日本政府は2004年に実施された無償資金協力「初等学校建設計画」の一部として「3月21日学校」を建設し、教室機材を供与しました。同小学校は2006年に生徒400名で開校しました。
2009年3月31日
大使がズボルニク市を訪問
-
罍二夫大使は、2009年3月31日にズボルニク市を訪問しました。この訪問において、大使はゾラン・ステヴァノヴィッチ・ズボルニク市長と会談を行い、日本とズボルニク市の協力関係について協議しました。
-
日本政府はこれまでズボルニク市に対していくつかの支援を行っています。2003年には、ズボルニク医療センター内の地域密着型リハビリテーション・センターにリハビリ機材を供与し、2005年には同医療センターに医療機材を供与しています。大使は同医療センターも訪問し、ステファノヴィッチ所長と会談を行いました。
-
また、大使はズボルニク市内のコズルク地区も訪問し、バニアノヴィッチ同地区長と日本が2005年に69,900ユーロを支援したコズルク環境改善計画について協議しました。また、大使は同地区内でミネラルウォーターや清涼飲料水を生産している企業ヴィティンカの生産施設を訪問しました。
2009年3月25日
日本政府、暖房修復・機材整備支援費用60,966ユーロをドニ・ヴァクフ第一小学校へ支援
-
3月25日、罍二夫大使とフソ・スシッチ-ドニ・ヴァクフ市長との間で「ドニ・ヴァクフ第一小学校教育環境改善計画」に関する贈与契約署名式を行いました。 これは日本政府の「草の根・人間の安全保障無償資金協力」を通じ、ドニ・ヴァクフ第一小学校に暖房設備及び教室内の機材を整備するため、60,966ユーロ(約9,998,424円)を限度とする支援を行うものです。
-
ボスニアの小学校は90年代の紛争当時、国連平和維持部隊の宿舎、あるいは国内避難民・難民の避難生活場所として利用されていた建物が多いため、建物の外部のみならず内部も被害を受けている学校が多くあります。
-
ドニ・ヴァクフ第一小学校クリチャ・クラ分校では、ボイラーが1979年製と古くラジエーターのパイプも一部破損したため、1996年から薪ストーブを使用しています。 しかし、生徒達の不注意によりやけどをする可能性もあり、また、すすで教室内の空気が汚れ生徒達の健康面に適した環境ではないため、セントラルヒーティングシステムを導入する工事を行います。
-
ドニ・ヴァクフ第一小学校本校は、1997年に建物は修復されましたが、教室内の机・椅子は20年以上前から使用されているため損傷が激しく、生徒達の服や肌を傷つけることがあるため、本計画では破損の激しいものを取り替えます。 本計画により、1216名の生徒と73名の教師・職員の教育環境と保健衛生環境が改善されます。
-
日本政府は1996年から現在に至るまで、初等教育整備のために約2千万ユーロをボスニア・ヘルツェゴヴィナに支援しています。
2009年3月23日
日本政府、暖房修復支援費用45,580ユーロをゴラジュデ市メフメダリヤ・マクディズダル小学校へ支援
-
3月23日、罍二夫大使とフセイン・ハリロヴィッチ-ゴラジュデ市メフメダリヤ・マク・ディズダル小学校校長との間で「ゴラジュデ市メフメダリヤ・マク・ディズダル小学校教育環境改善計画」に関する贈与契約署名式が行われました。 これは日本政府の「草の根・人間の安全保障無償資金協力」を通じ、メフメダリヤ・マク・ディズダル小学校に暖房設備を整備するため、45,580ユーロ(約7,475,120円)を限度とする支援を行うものです。
-
ボスニアの小学校は90年代の紛争当時、国連平和維持部隊の宿舎、あるいは国内避難民・難民の避難生活場所として利用されていた建物が多いため、建物の外部のみならず内部も被害を受けている学校が多くあります。
-
メフメダリヤ・マク・ディズダル小学校は1996年に改築されましたが、当時は資金不足により十分な能力を持つボイラーを設置することができず、体育館や保育園などを含めて全校舎に暖房を行き渡らせることができない状態が続いていました。 そこで本計画では新しいボイラーを設置し、全校内に暖房が行きわたるよう暖房設備の修復工事を行います。 また、ボグシュチ分校では薪ストーブが使用されていますが、すすで教室内の空気が汚れ生徒達の健康に適した環境ではありません。 また、生徒達の不注意によりやけどをする可能性もあります。 本計画では本分校の暖房を薪ストーブから、セントラルヒーティングシステムを導入する工事を行います。 本計画により、冬が長いゴラジュデ市の本小学校の生徒520名と教師・職員約60名の教育環境と保健衛生環境が改善されます。
-
日本政府は1996年から現在に至るまで、初等教育整備のために約2千万ユーロをボスニア・ヘルツェゴヴィナに支援しています。 .
2009年3月19日
日本政府、暖房修復・機材整備支援費用50,988ユーロを ゼニツァ市アレクサ・シャンティチ小学校へ支援
-
3月19日、罍二夫大使とメディハ・フルスティッチ-ゼニツァ市アレクサ・シャンティチ小学校校長との間で「ゼニツァ市アレクサ・シャンティチ小学校暖房修復計画」に関する贈与契約署名式が行われました。 これは日本政府の「草の根・人間の安全保障無償資金協力」を通じ、アレクサ・シャンティチ小学校の暖房設備及び教室内の機材を整備するため、50,988ユーロ(約8,362,032円)を限度とする支援を行うものです。
-
ボスニアの小学校は90年代の紛争当時、国連平和維持部隊の宿舎、あるいは国内避難民・難民の避難生活場所として利用されていた建物が多いため、建物の外部のみならず内部も被害を受けている学校が多くあります。 アレクサ・シャンティチ小学校では、約1000人の国内避難民・難民が校舎内で一時避難生活を送っていたため、建物内部も被害を受けています。
-
アレクサ・シャンティチ小学校の暖房設備は、30年前に設置されたもので老朽化が激しく、ボイラーが十分に機能しないため、全校内を暖かくすることができない状態にあります。 そこで本計画では新しいボイラーを設置し、全校内に暖房が行きわたるよう暖房設備の修復工事を行います。 これにより、冬が長く厳しいゼニツァ市の本小学校の生徒640名と教師・職員約50名の教育環境と保健衛生環境が改善されます。 また、教室内の机や椅子は30年以上使用されているため、特に損傷の激しい生徒用机・椅子なども教育環境改善のため新しいものに入れ替えられます。
-
日本政府は1996年から現在に至るまで、初等教育整備のために約2千万ユーロをボスニア・ヘルツェゴヴィナに支援しています。
2009年3月16日
「日本政府、高機能救急車整備支援費用48,089ユーロをゼニツァ診療所へ支援
-
3月16日、罍二夫大使とフェリド・アリッチ-ゼニツァ市ゼニツァ診療所所長との間で「ゼニツァ診療所救急車整備計画」に関する贈与契約署名式が行われました。 これは日本政府の「草の根・人間の安全保障無償資金協力」を通じ、ゼニツァ診療所における救急車両を整備するため、48,089ユーロ(約7,886,596円)を限度とする支援を行うものです。
-
本計画では、心臓疾患の応急処置を可能にするため、心電図、除細動器(モニター・プリンター・バッテリー付き)、心肺蘇生セット、強力ライト、電源装置などの特別医療機材が搭載された高機能救急車が購入されます。 購入される救急車両は前輪駆動車であり、山間部や道路事情が悪い場所、そして積雪の多い場所などへ素早く対応できるようになります。 これにより、人口約13万人のゼニツァ市の地域医療環境が改善されることが期待されます。
-
日本政府は1996年から現在に至るまで、医療機関整備事業のために約5千万ユーロをボスニア・ヘルツェゴヴィナに支援しています。