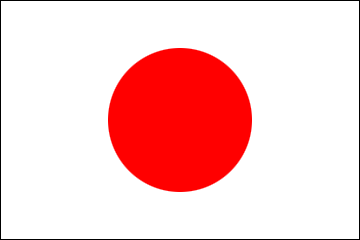各種届出
令和7年4月22日
注意事項
戸籍に関わる届出(出生届、婚姻届など)において、遠隔地にお住まいの方で、郵送による届出を希望される場合は、当館まで事前にご相談下さい。
なお、出生証明書、婚姻証明書、国籍証明書は原本を提示していただく必要がありますが、原本を1部しかお持ちでない場合などは、当方にてコピーし、原本はお返しします。
令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、届出期限が変更される届出があります。詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されます(2025年5月26日から)
戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について(2024年4月1日から)
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(2024年4月1日から)
出生届
出生日を含めて3ヶ月以内に出生届を当館へ直接、又は本籍地の市区町村役場に郵送で届け出て下さい。出生児に外国の国籍も併せて取得している場合は、(例えば、父または母がボスニア・ヘルツェゴビナ国籍である場合等)、この届出期限内に日本国籍を留保する意志表示(出生届の国籍留保欄に署名捺印)をしなければ日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。
必要書類(原本を各2通)
・出生届(大使館窓口に用紙があります)
・外国官公署発行の出生登録証明書、又は医師作成の出生証明書(当館で作成した様式をご利用いただけます。)
・同和訳文(様式)
必要書類(原本を各2通)
・出生届(大使館窓口に用紙があります)
・外国官公署発行の出生登録証明書、又は医師作成の出生証明書(当館で作成した様式をご利用いただけます。)
・同和訳文(様式)
婚姻届
日本人間の婚姻
届出期限は婚姻成立日より3ヵ月以内です。
日本人と外国人間の婚姻
必要書類については、婚姻する方式と新たに設定する本籍地等により、必要書類及び部数が異なるので大使館までお問い合わせ下さい。
- 日本人同士が日本の方式により婚姻する場合
- 日本人同士が外国の方式により婚姻した場合
届出期限は婚姻成立日より3ヵ月以内です。
日本人と外国人間の婚姻
- 日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
- 日本人と外国人が日本の方式(法律)によって婚姻する場合
必要書類については、婚姻する方式と新たに設定する本籍地等により、必要書類及び部数が異なるので大使館までお問い合わせ下さい。
離婚届
日本人間の離婚
日本人と外国人間の離婚
必要書類については、離婚する方式と新たに設定する本籍地等により、必要書類及び部数が異なるので大使館までお問い合わせ下さい。
- 日本人同士が日本の方式により離婚する場合
- 日本人同士が外国の方式により離婚した場合
日本人と外国人間の離婚
- 日本人と外国人が外国の方式によって離婚した場合
- 日本人と外国人が日本の方式(法律)によって離婚する場合
必要書類については、離婚する方式と新たに設定する本籍地等により、必要書類及び部数が異なるので大使館までお問い合わせ下さい。
不受理申出
自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)
対象となる届書は、届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届となります。
ただし、外国法により成立した、又は、裁判により確定したことによる「報告的届出」は、この不受理申出をしていても受理されます。詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。
○申出人
不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。
○申出先
在外公館(注)、日本の市役所又は町村役場
(注)外国籍の方が申出する場合
外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが、在外公館では、外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは、日本人のみとなります。)
従いまして、外国籍の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、(1)申出をする旨、(2)申出の年月日、(3)申出する者の氏名、出生年月日、住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書を提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場の担当部署に適宜問い合わせてください。
○申出方法
申出人本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が在外公館、市区町村役場に出頭して行う必要があります。
不受理申出は、申出人本人からしか行うことができませんので、郵送や代理人による申出はできません。ただし、本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、申出を予定している在外公館、市区町村役場までお問い合わせください。
○申出に必要なもの
(1)不受理申出書 2通(在外公館の領事窓口にあります。)
(2)申出人のご本人確認書類(旅券等)
(3)15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通
○不受理申出の期限
不受理申出の有効期間は、申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか、不受理申出の「取下げ」をしない限り、無期限です。
○不受理申出書及び記載例
・「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
対象となる届書は、届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届となります。
ただし、外国法により成立した、又は、裁判により確定したことによる「報告的届出」は、この不受理申出をしていても受理されます。詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。
○申出人
不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。
○申出先
在外公館(注)、日本の市役所又は町村役場
(注)外国籍の方が申出する場合
外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが、在外公館では、外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは、日本人のみとなります。)
従いまして、外国籍の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、(1)申出をする旨、(2)申出の年月日、(3)申出する者の氏名、出生年月日、住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書を提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場の担当部署に適宜問い合わせてください。
○申出方法
申出人本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が在外公館、市区町村役場に出頭して行う必要があります。
不受理申出は、申出人本人からしか行うことができませんので、郵送や代理人による申出はできません。ただし、本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、申出を予定している在外公館、市区町村役場までお問い合わせください。
○申出に必要なもの
(1)不受理申出書 2通(在外公館の領事窓口にあります。)
(2)申出人のご本人確認書類(旅券等)
(3)15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通
○不受理申出の期限
不受理申出の有効期間は、申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか、不受理申出の「取下げ」をしない限り、無期限です。
○不受理申出書及び記載例
| ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約) |